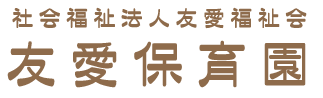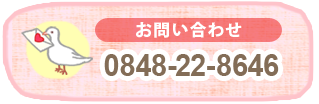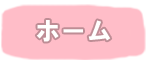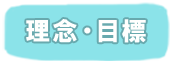園長のひとりごと
進化と成長
2019-01-05
長きに亘る人類の進化を縮尺し、一人の人間の成長に当てはめた時、人類がどのようにして進化してきたのかを振り返ることで、人はどのような過程をたどれば、成長していけるのかを知ることができる。人類を進化させた大きな要因は2つ。それは言語と道具である。言語の発達でコミュニケーションをとることが可能となり、集団として生活し、助け合いが生まれた。そして道具を使い、効率を上げ、生活を豊かにしながら、人口を増やしていった。また同時に言語と道具を使うことが、脳を刺激し、肥大化させていった。この人類進化の始まりを、一人の人間の成長に当てはめた時、乳幼児期に必要な生活形態が自ずと見えてくる。それは早期の言語による関わり、そして道具を使うことができる環境設定である。進化と成長、時間の規模は大きく異なるが、この2つの要素が脳を強く刺激し、成長させることに変わりはない。そして光、闇を知り、気温、季節を感じ、時、数、量と不変の真理を学んだ後、高度なものに発展していく進化過程も、現代の子どもたちの成長に当てはめることができる。これからいくら時代が進んでも子育てに最新式は無く、有るのは、しっかりと辿った過去、現在から未来はつくられていくという事実だけである。進化の歴史には何万年も続く様々な試練、困難があり、それを乗り越えて現在がある。縮尺した一人の人間の成長に置き換えれば、何万年は数日である。今日からでも遅くはない。現在を見直すことは、必ず豊かな未来へつながっていく。
幼児期の学び
2018-11-16
子どもたちは、日々、感動を求めています。幼児期の学びとは、記憶ではなく、感動、幸せの数で作られていきます。だからといって、多種多様な感動が必要なわけではありません。同じ絵本、同じ景色、同じ食べ物、子どもたちは、自分が好きなことで何度も感動します…してくれます。決して忘れてしまったわけではなく、「もー知ってる」という記憶は、一旦置いて、感動を優先しています。そして、この感動という学びの証しは、表情と眼差しを見ればすぐに解ります。子どもたちの笑顔は、学びの成功を教えてくれます。幼児期の過ごし方、幼児教育ということを難しく考えず、子どもたちの段階的な発達を理解して、笑顔を目標に、優しく、ゆとりのなかで、行動、いたずら!?を見守ってあげてください。それが、子どもたちにとっては、一番の幸せであり、学びだと思います。「おーでたー。おー見えたー。う~ん美味しー。」繰り返される感動、繰り返される笑顔♪我が家だけの幼児教育を、ぜひ子どもと一緒に見つけて下さい。
道徳
2018-09-12
今年から、小学校では「特別の教科道徳」がスタートしています。来年からは中学校でも始まる予定です。釈迦に説法になりますが、道徳とは簡単にいえば、善悪を知るということです。この道徳の授業に力を入れる背景には「いじめ」という問題があります。友達の心の痛みを知る、差別や偏見をもたない人に成長してほしい、この願いが形となって今年からスタートしています。就学前教育に於きましても、現在、新しい保育指針の幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿のなかに「道徳性・規範性の芽生え」という項目があります。当然のことですが、道徳、善悪を知るとは、就学前の幼児期にすでに始まっています。でもここでお話ししたいのはもう少し先の道徳です。話が少し逸れますが、今、私がほしいと考えているもののランキング1位はロボットです。今年、ある電気メーカーからAI搭載の犬型のロボットが発売されています。パソコン・スマホ等で動画をみることもできます。私が、この動画を実際見て感じたこと、それは「まさに子犬」です。動きや表情、そしてAI搭載で学習能力もあり、驚くべき時代の到来だと思います。しかしこのロボットに命はありません。人間が作ったものでしかありません。もうひとつ別のロボットの話になりますが、アメリカには進化した人型ロボットがあります。これもパソコン・スマホで動画をみることが出来ますが、歩行、バランス力、ジャンプ力、びっくりする動きをします。しかしその開発過程では、機能向上のテストとして、ロボットがもっている箱を、人が木の棒で叩き落としたり、邪魔をしたり、ロボットを蹴って転がしたり、足をひっかけて転がしたりという内容のものも含まれています。開発中の試験ですので仕方がないことですが、この動画をはじめて見たときに「かわいそう」と思った自分に不思議な感覚を覚えました。命も存在しないのに、ロボットなのに、なぜ?人間のような形だから?犬のような動きだから?本当に不思議な感覚でしたが、この時に道徳という言葉と少し先の未来が頭に浮かびました。命がないものは、粗末に扱ってもいい、所詮ロボット、役に立たなくなったら、捨てようが、壊そうが、又、ストレスが溜まったら、そのはけ口として、叩いたり、蹴ったりしても所詮、命は存在しないのだから、なにをしても構わない。「でも私たち、命のあるものは大切にするよう習いましたし、実際、命は大切にしていますよ…?」今、目の前にいる子どもたちに、近い未来、命あるもののように生活の一部に溶け込んでいるであろうロボットを、粗末、乱暴に使い、扱い、ストレスのはけ口として暴力を振るうような大人になってほしくはありません。しっかりと心、魂を持った人間として、本当の道徳とはなにか、そして命、心の有無ではなく、その時代に沿った新しい枠組みの道徳、善悪を考え、個人個人で哲学できるような大人になってもらいたいと思います。これから時代は大きく変わっていきます。環境問題から、国際問題、そして人口問題、科学の急激な進歩、少しでも、想像が出来る未来があるなら、それをいち早く子どもたちに、何らかの環境として体験させてあげたい。なので、ロボットがほしいなーと、周囲に反対されながら、ひとりごとのように思っている今日この頃です。
方言じゃけー
2018-08-02
子どもたちは、よく親(大人)の真似をします。言葉やしぐさ、興味をもったことはすぐに真似したくなります。家で見るテレビ番組、CMも、見て聞いて覚えたフレーズを何度も繰り返し楽しみます。そのフレーズは内容も音程も上出来で、何の番組かCMか、すぐに理解できます。「よく覚えているな~」と感心させられますが、ふと思うと、テレビ番組、CMは多くが標準語で作られています。それを真似している子どもたちも、テレビそのままに標準語です。しかし、日常の会話では、流調に出てくる方言に、よく驚かされます。この方言は言葉が出始めた頃から、端々に現われてきます。子どもたちは、テレビやCMから聞こえてくる言葉をコミュニケーションツールとして覚えてはいません。単なるフレーズであり、セリフであり、一時的なものなのです。日常で使う実用的で通じる言葉は、生で新鮮なもの(方言を多く含む)を毎日求め、生活の環境から吸収しているのです。親子の会話、赤ちゃんへの語りかけ、愛情をもってリアルな方言で、たくさん話してあげてください。時には、真似られている自分の方言、言葉遣いに反省させられることもあると思いますが、その改善は追々ということで(笑)。
三つ子の魂百まで
2018-07-14
平均寿命、百歳の時代が迫っている。百歳といえば、昔から「三つ子の魂百まで」とよく言われる。三つ子といえば約3才、それまでの成長・そして性格が、良くも悪くも長く人生に影響を与えるという例えである。しかし幼き頃のこの年月を記憶している大人はどのくらいいるのだろうか。それは皆無に等しい。結論「三つ子の魂」創りの記憶は残らない…残らなくてもよいのである。生まれてから約3年の間に、子どもたちは、自らの意思で身体をほぼ自由に動かせるようになる。そして見る、聞く、感じる、あらゆる能力も同時に発達していく。これらすべてが新鮮で、楽しく、自由で、この時期に訪れる喜びは測りしれない。この現われてはすぐに消える喜びの一つ一つが、「百まで通じる魂」を創っていく大切な体験なのだ。子どもたちは、愛・信頼・感謝の心を備えた高性能で長期保証の魂創りを目的に、周囲に目を光らせ、時には汚れ、時には怪我をし、そして怒られながらも懸命に感動体験、喜びを探し求めているのだ。一見無意味を感じさせる子どもたちの動きは、しっかりと一世紀先へ繋がっている。